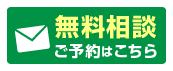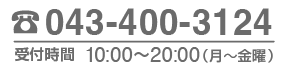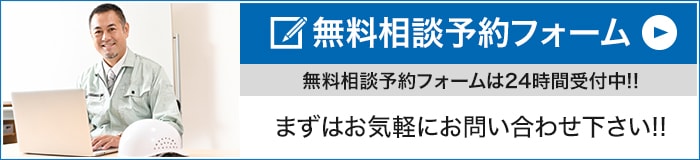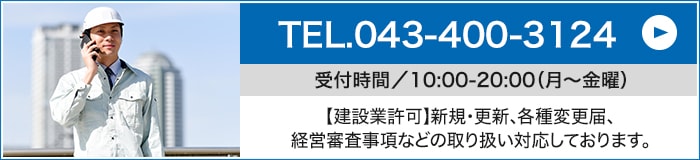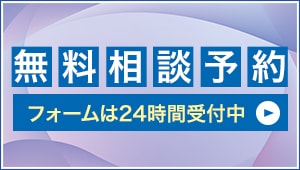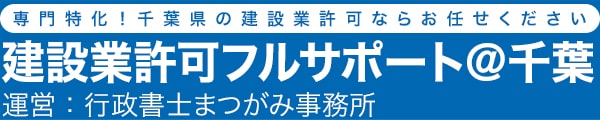建設業許可の一本化とは?許可業種の数が2つ以上の場合は管理がスマートに!
建設業許可の一本化(許可の有効期間の調整)とは、取得する業種が2つ以上になるときに行うことによってメリットがあります。
- 許可の一本化が必要になる場面
- 許可の一本化によるメリット
- 許可を一本化するタイミング
を説明していきます。
許可の一本化が必要になる場面
まず、建設業の許可を「業種追加」などで取得した場合、すでに持っている許可と、業種追加した許可では「許可年月日」が異なってしまいます。
そのため、許可年月日が異なってしまうという事は、更新の時期も許可ごと。つまりバラバラに更新することになってしまいます。
このように「内装工事業」「解体工事業」「電気工事業」の3つの許可をそれぞれ取得した場合、それぞれの更新のタイミングで申請することになります。
- 更新のスケジュールを3つとも把握する必要があるため、労力が非常にかかる
- 更新時期を失念し、許可の効力が失効してしまう可能性も!
- それぞれ更新するため、更新手数料(証紙代)が3回発生する
といったように、費用や事務作業が増えてしまい本業に専念する時間なども少なくなってしまいます。
許可の一本化によるメリット
取得した許可の数が増えると管理が煩雑になり、費用が数回になり更新手数料を支払う回数も額も増えてしまいます。
許可の一本化(許可の有効期間の調整)を行うと次のようになります。
- 更新をする申請が一本化され申請、管理スケージュールが分かりやすくなる
- 3回発生していた「更新手数料」が1回で済む
このように煩雑になっていた「期日管理」、複数回発生していた更新手数料の「費用」に関してメリットがあります。
許可を一本化するタイミング
ではどのタイミングで、許可の一本化を行うのが良いのか?そのタイミングと理由を説明していきます。
- もっとも一般的なタイミングは、一番最初に許可を取得した「内装工事業」の更新のタイミング2035年4月1日で、他の2種類(解体工事業、電気工事業)の許可の更新も一緒に行うものです。
- このタイミングで更新の一本化を行うと、解体工事業と電気工事業の更新まで期間が残っています。
しかし、その分更新手数料が1回分で済み、また次回の更新手続きも1回で済むことになります。 - 許可が「一般」と「特定」の場合は、それぞれの更新料が必要になります。
このように、許可の一本化をすることにより、管理もシンプルになり更新忘れも防げるようになります。
その他にも「許可更新の概要」や「更新する際の注意すべきポイント」なども参考にしていただければと思います。
また、許可の一本化(許可の有効期間の調整)に関しては、建設業許可の手引き「千葉県」「東京都」をはじめ、各自治体にの手引きにも記載されていますので、気になる方は確認してみてください。
建設業許可の一本化のまとめ
いかかでしたでしょうか?
建設業許可の一本化について解説してきました。
許可の一本化の手続きは難しく、テクニカルな要素もありますので、時間とお金のコスト削減をしたい!
といった建設業者様は、ぜひ建設業に専門特化した当事務所にご相談ください。